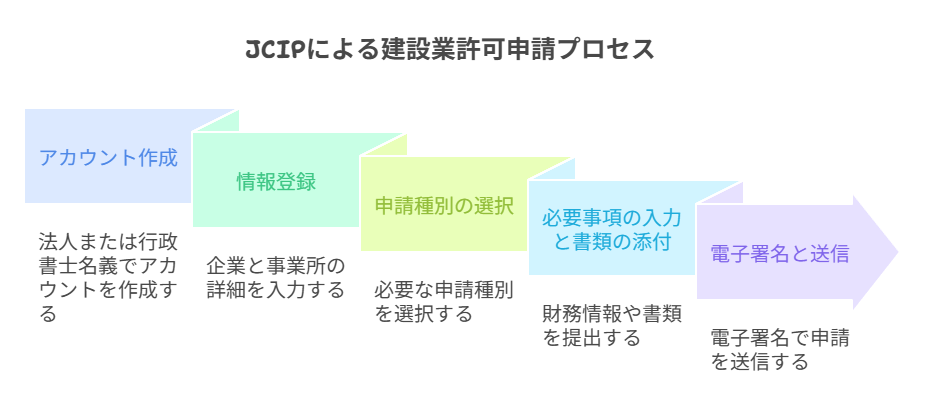✅ はじめに
建設業許可を取得する際、専任技術者の配置は欠かせない条件の一つです。そして専任技術者として認められるためには、「資格」または「実務経験」が必要です。
この記事では、「資格ではなく、実務経験で専任技術者要件を証明する場合」について、どのような書類が必要で、どう収集するかを、ベテラン行政書士の視点から詳しく解説します。
✅ 実務経験が必要なケースとは?
まず、専任技術者になるには以下のいずれかの要件を満たす必要があります:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 国家資格等 | 施工管理技士、建築士、技術士などの指定資格保有 |
| 実務経験 | 原則10年以上(学歴・職歴により緩和あり) |
本記事では、資格がない場合に必要な「実務経験10年(高卒は5年・大卒は3年に短縮されるケースあり)」を証明するための書類に焦点を当てます。
✅ 実務経験証明の基本的な考え方
建設業法では「専門工事に関する実務経験」を「10年以上継続して積んでいること」を証明できれば、専任技術者として認められます。
証明に必要なのは、次の2点です:
- どのような工事をしていたのか(工種)
- いつ、どの会社で、どのくらいの期間行っていたのか(勤務・実施期間)
✅ 実務経験証明に必要な主な書類(具体例)
以下のうち、複数の資料を組み合わせて証明するのが基本です。
① 工事関係書類
| 書類名 | 内容 | 発行元 |
|---|---|---|
| 請負契約書 | 請負金額・発注者・施工内容が記載されている | 元請会社、発注者 |
| 工事台帳 | 工事ごとの内容・担当者・期間が記録されている | 勤務先企業 |
| 注文書・請書 | 発注・受注のやりとり | 取引先または社内保管 |
| 完成検査報告書 | 工事完了を証明する資料 | 元請業者、監督官庁 |
| 写真付きの施工記録 | 担当者名や期間のわかる現場写真 | 勤務先企業の現場記録 |
② 勤務証明関連書類
| 書類名 | 内容 | 発行元 |
|---|---|---|
| 在職証明書 | 勤務期間と職種(技術系)を記載 | 勤務先企業 |
| 給与明細・源泉徴収票 | 継続勤務の証明に使用 | 勤務先または税務署 |
| 雇用契約書・採用通知書 | 勤務開始日・職務内容の記載 | 勤務先 |
| 健康保険・厚生年金の記録 | 雇用実績を客観的に証明できる | 日本年金機構、市町村 |
✅ 書類の収集方法とポイント
◆ ステップ1:勤務先に依頼
- 過去の勤務先に在職証明書や工事台帳などを依頼
- 複数社勤務していた場合は、通算10年の期間が確認できるよう全社分集める
🔎 注意:会社が倒産している場合は、税務署から源泉徴収票などを取り寄せることで代替可能
◆ ステップ2:本人保管の資料を整理
- 工事写真、注文書の控え、古い給与明細なども有効
- 少しでも関連がありそうな書類は、一旦すべてコピーして整理
◆ ステップ3:年金記録・住民票履歴の取得
- 勤務期間の整合性確認のために、年金加入記録と住民票の履歴付き証明書を用意
- 転職や転居が多い方ほど有効です
✅ 行政庁が重視するポイント
| チェック項目 | 審査の観点 |
|---|---|
| 工事内容の具体性 | 施工内容が申請業種と一致しているか |
| 証明資料の客観性 | 在職証明+契約書等で「第三者が確認できる形」になっているか |
| 実務の継続性 | 途切れのない形で10年間相当の実績があるか |
📌 「同一業種で10年の証明」は単なる在職年数ではなく、「技術者として該当工事に従事していた」ことが重要です。
✅ よくあるQ&A
Q. 同じ会社で経理から施工管理に異動しましたが、全部カウントされますか?
➡ いいえ。実務経験として認められるのは「技術系職務に従事していた期間のみ」です。
Q. 工事写真や注文書だけでは不十分ですか?
➡ 写真・契約書だけでは「勤務期間」が不明確なため、在職証明書や年金記録とのセットが必要です。
✅ まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 必要年数 | 原則10年(高卒5年、大卒3年に短縮可) |
| 書類の種類 | 在職証明書、工事台帳、契約書、写真、年金記録など |
| 証明のコツ | 複数資料を組み合わせて「勤務期間」と「業種一致」を両立すること |
✅ 実務に不安がある方へ
実務経験での申請は、証明方法が複雑で、自己判断では不許可になるリスクも高いのが現実です。
経験豊富な行政書士なら、書類の整備から行政庁との事前相談、申請書の作成までトータルで対応可能です。
建設業許可取得の第一歩として、まずは実務経験の棚卸しから始めましょう!
📌 ご相談は随時受付中。証明書類のチェックリストもご用意しています。お気軽にお問い合わせください!
の要件を満たさない-visual-selection.png)